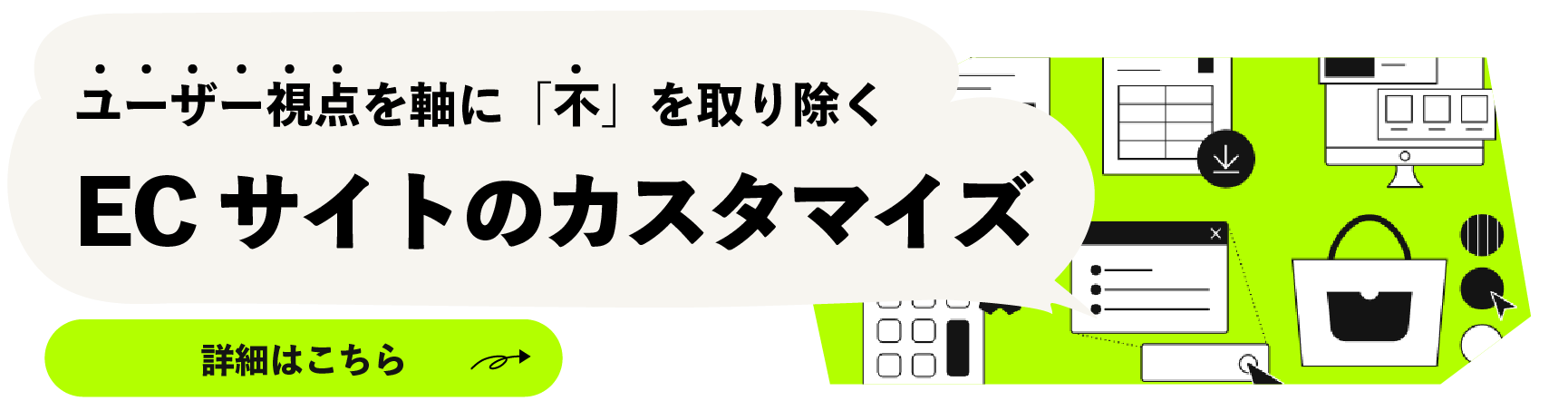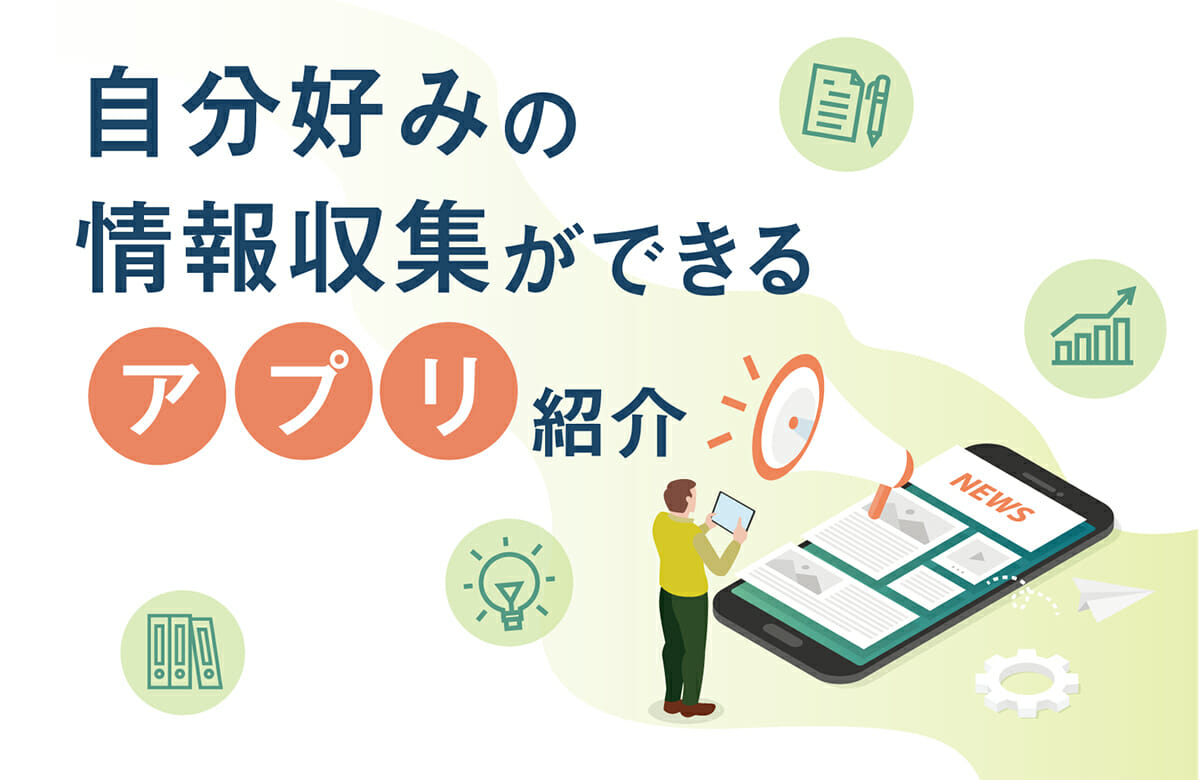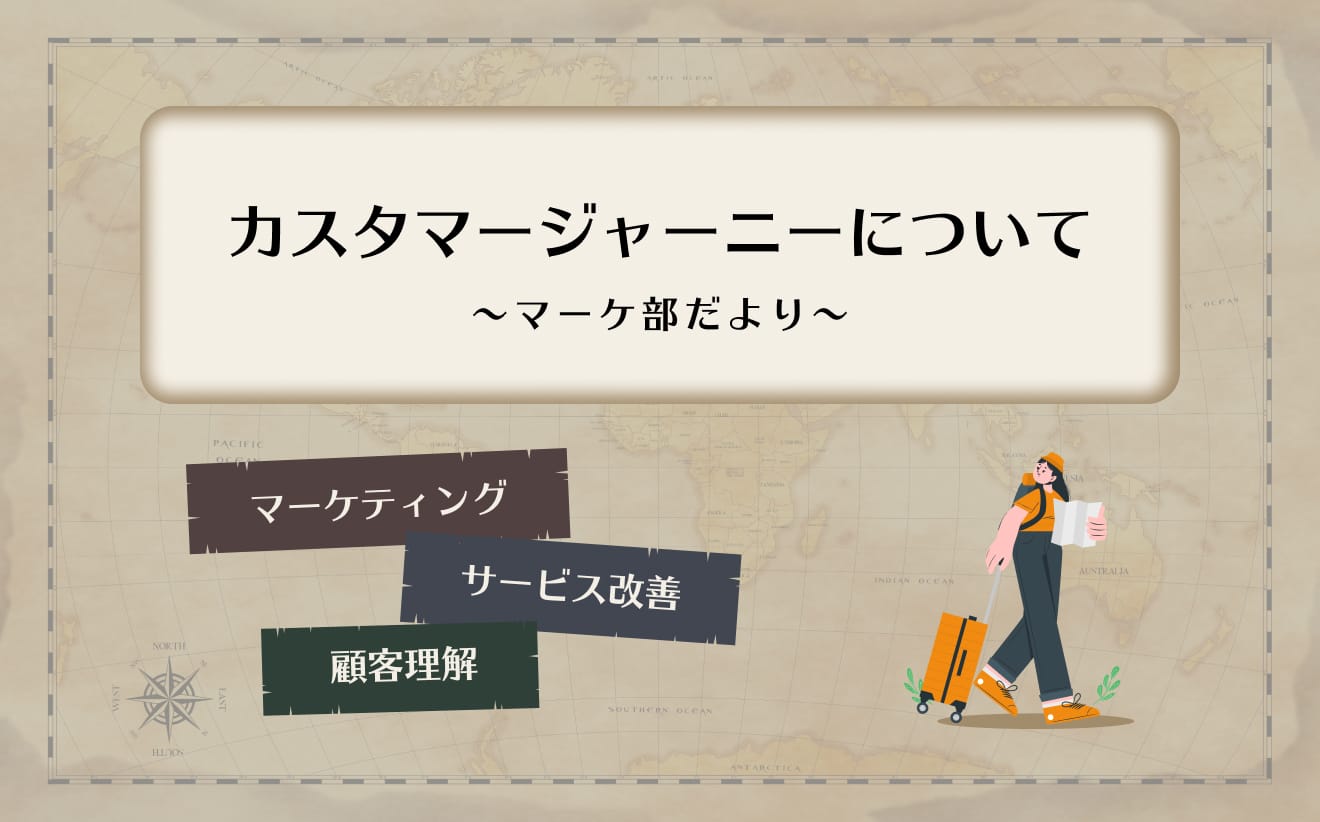こんにちは、NUSEEKのいわやです。いつの間にか梅雨も明け、本格的な夏が始まっています。
夏といえば!アイスコーヒー!ということで、自宅用にコーヒーマシンを新しく買いたい…と思いつき、Amazonで「コーヒーメーカー」と検索してみました。
すると、ざっと5万件近い商品がズラリ。条件に合いそうな商品をいくつか見ていた中で、ふとある1台に目が留まりました。
サイズやお手入れのしやすさなど、自分が求めていた条件を満たしているのはもちろんですが、何より印象に残ったのは、「これがあると朝の時間がちょっと楽しくなりそうだな」と、未来の生活が自然と思い描けたこと。
「なぜ数ある商品の中でこれだけ惹かれたんだろう?」そう考えてみると、その商品説明には“機能”だけでなく、“ベネフィット”がしっかりと書かれていたことに気づきました。
ベネフィットとは、「その商品を使うことで、お客様がどんな良い体験や気持ちを得られるのか」ということ。つまり、“スペック”ではなく、“変化”を伝えることこそが、選ばれる理由になるのです。
今回は、そのベネフィットの基本と、より伝わる商品説明のための考え方をご紹介します。
「ベネフィット」って何?
ベネフィットとは、「お客様がその商品を手に入れることで得られる価値」のことです。単なる機能やスペックだけなく、「使ったときにどう便利か」「どんな気持ちになれるか」といった価値も含みます。
お客様が本当に知りたいのは、
❌「何ができる商品か」
⭕「それを使うと、自分の生活がどう変わるのか」
ベネフィットを伝えることは、「この商品は、あなたにとって価値がありますよ」と伝えること=選ぶ理由をつくることなのです。
ベネフィットには、2種類ある
ベネフィットには、「機能的ベネフィット」と「情緒的ベネフィット」の2つの種類があります。
機能的ベネフィットとは
商品を使うことで得られる物理的で計測しやすいベネフィットのことで、たとえば「軽い」「早い」など、商品のスペックに関連したものです。
【例】
・軽量 → 持ち運びが楽になる
・早い→牛丼の提供時間
情緒的ベネフィットとは
商品を使うことで得られる感情的・心理的な満足感や幸福感のことで、「気分が上がる」「自分らしさが表現できる」といった人の心情に訴えかける価値です。
【例】
・ブランドバック → 持っていることで自信が持てる、気分が上がる
・限定商品→自分だけが持っている、選ばれた人だけのものという優越感・満足感
では、コーヒーメーカーの例を使って、ベネフィットを意識した商品説明に書き直してみましょう。
【Before】機能的ベネフィットだけの説明
このコーヒーメーカー、抽出温度90度で最適な味を実現します
【After】情緒的ベネフィットも加えた説明
朝の忙しい時間でも、ワンタッチでカフェのような本格的なコーヒーが楽しめます。90度の最適温度で抽出するから、コーヒー豆本来の香りと深いコクが味わえて、一日の始まりが特別な時間に変わります
どうでしょうか?後者のほうが、ぐっと「自分ごと」としてイメージしやすく、「欲しい!」と感じませんか?
人間の欲求から考える、ベネフィットの見つけ方
ベネフィットとは「お客様にとっての価値」ですが、その価値とは一体なんでしょうか?
それは、人間の根源的な欲求に紐づいています。アルダファー氏が唱えたERG理論によると、人の欲求には大きく分けて3つのパターンがあると言われています。
E(生存欲求):生活を便利に、安全にしたい 「時短したい」「疲れを減らしたい」「安心したい」など、日常の困りごとを解決したい欲求
R(関係欲求):人とのつながりを大切にしたい 「家族に喜んでもらいたい」「友人と楽しい時間を過ごしたい」など、人間関係を豊かにしたい欲求
G(成長欲求):もっと素敵な自分になりたい 「新しいことを学びたい」「自分らしさを表現したい」など、自分を高めたい欲求
理想的には、この3つの欲求すべてを満たすようなアプローチの商品説明ができると、お客様により強く響く内容になります。
まとめ ベネフィットで「選ばれる理由」をつくろう
今回は、「ベネフィットを伝えることが、選ばれる商品説明のカギになる」というテーマでお届けしました。ECサイトには、似たような商品がたくさん並んでいます。その中でお客様に選んでもらうには、「何ができるか」だけでなく、「それによってどんな良い変化が得られるか」=ベネフィットをしっかり伝えることが重要です。
次回は、このベネフィットを活かして、より効果的に商品を届けるための「セグメンテーションとターゲット設定」についてご紹介する予定です。どうぞお楽しみに!